明治 大正を生きた、文芸評論家で翻訳家、小説家の内田魯庵と「日本橋・丸善」〜 夏目漱石との交流
作家 三島由紀夫が自ら命を絶つ9カ月前
英国の翻訳家、ジョン・ベスターと対談した
肉声テープが、赤坂TBS内にて発見された。

▶︎ 三島由紀夫(1956年撮影;31歳)
出 典;Wikipedia
約1時間20分にわたり自身の死生観、
文学論などを淡々と語るそのテープ。
その日の朝に終えた、と語っていることから
1970年2月19日に録音されたものとみられている。
数多くの作品を遺した三島。
2005年には、学習院中等科在学中の
三島由紀夫文学館に所蔵される未発表作品の中から
発見され話題となった。
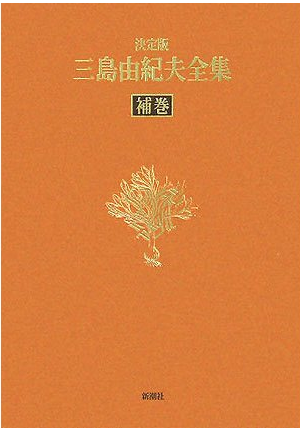
▶︎『決定版 三島由紀夫全集補完』(新潮社刊行)
この中に、2005年発見の作品が収録されている
『決定版三島由紀夫全集補完』に収録された
1937年(昭和12年)執筆のその作品のタイトルは
『 我はいは蟻である 』
主人公は、生まれたばかりの働き蟻。
重たいビスケットを運んだり、仲間の長老に
敵対する蟻のことを聞かされたりーー
なんだかどこかで聞いたことのある
そのタイトルに、思わず耳を疑ったことは
いうまでもない。
似ていると感じた作品は他にもある。
明治大正を生きた、文芸評論家で
翻訳家、小説家の内田魯庵の書いた
『犬物語』である。
慶応4年(1868年)江戸下谷車坂六軒町
(現在の台東区東上野3丁目付近)に
誕生した、内田魯庵(本名;貢)。

出 典; Wikipedia
彼の父・内田鉦太郎(のち正と改名)は、
父・鉦太郎は上野市中を守る「彰義隊」に参加する
そのまま1ヶ月の間、どこかへ姿を隠してしまう。
それからほどなくして明治の世となり、
父・鉦太郎は東京府に出仕するも
不安定な相場の世界へとのめり込んでいく。
父は蛎殻町のコメ相場で失敗し
手放すことになった。
そんな父を反面教師としたのだろうか。
魯庵は文学の道を志す。
文芸評論で名を挙げた魯庵は
書籍部顧問として入社。
その先駆的な知識や教養を活かし、
丸善のPR雑誌である『学の燈』(のちに『学鐙』)
への執筆・編集を精力的におこなっていく。

▶︎ 『学鐙』 第113巻 第4号
2012年より年4回の季刊発行となるも
明治30年3月から続く、その “ 学びの燈(ともしび)” は、
今日も赤々と灯り続ける
これに魂を吹き込んだのは、福沢諭吉。
それに肉づけをした者こそ、
じつに内田魯庵であった
(『丸善百年史』昭和55年発行より抜粋)
20世紀の丸善にとって大変に重要だった
という、内田魯庵の存在。
現在の丸善でも、彼の「偉勲」を
目にすることができる。
今も “ 丸善の象徴 “ として
お買い上げ袋に印刷されている「フクロウ」

MとZの組み合わせで「フクロウ」を模った
マークを使用しているという。
このモデルとなったのは「知恵の女神・アテナ神」と
その使者である「フクロウ」
これらを “ 丸善の象徴 ” として考案したのは
内田魯庵ではないか、と出版人で
丸善OB の八木佐吉氏はそう推測する。

▶︎ 八木佐吉著『書物往来』(東峰書房刊行)
ご子息・正自さんのご厚意により、いただいた1冊。
丸善の歴史を後世へと遺した、佐吉さんの功績を忘れてはならない
大正 8年(1919年)
創業 50周年
丸善では、過去に功績のあった
先人たち6氏を選出。
3月22日にその追悼会が
本郷の駒込・吉祥寺にて執行された。

▶︎ 本駒込「諏訪山 吉祥寺」
( 東京都文京区本駒込3-19-17 )
旧幕府軍総裁・榎本武揚がその妻多津とともに、静かに眠る吉祥寺
伊村克巳(岩村藩士)
金沢廉吉(岩村藩士)
三次半七(江戸出身・岩村藩士の従者)
斎藤豊八
松下鐡三郎(豊橋藩士・2代目社長)
しながら、見習生たちに、電話での話し方や
取り扱い方を教えていたという
多門(おおかど)傳十郎。
丸善OBで祖父の親友だった、
間宮不二雄さんは
「いつも長い髭をたくわえ、
黒木綿の紋付袴を着用され
とても身だしなみの良い老人だった」
こう当時を振り返っている。
多門氏は、三代目社長の小柳津要人同様
岡崎藩士の家柄だった。
本多岡崎藩家臣団で、私の五世祖父の家系同様、
本多平八郎忠勝公時代から、その名を連ねる名家
(700石)で、子息・猶次郎とともに、
丸善に勤務していた。

出 典;Wikipedia
敷地内の「龍城館」には、藩士やその家族が暮らせる邸宅があった
関わり合う仲間を大切にーー
どんな時も先人への感謝の気持ちを忘れない、
そうした「三河武士」の心意気と、折り目正しさを
1人ずつが大切にしていたのではないか、そう思う。
この追悼会執行とともに、社員には祝意として
等級に応じ「フクロウ文鎮」ほか全3種の
新海竹太郎作・記念品が配られた。

▶︎ 新海竹太郎作「フクロウ文鎮」
新海竹太郎は、当時「帝室技芸員」
優秀な美術家・工芸家に対して
宮内省(戦前)から与えられる「顕彰」を
背負った、日本を代表する著名な彫刻家だった。

▶︎ 「フクロウ文鎮」の裏面
丸善50年記念の文字が刻まれている
社員1人ひとりに配られた、社のシンボル。
丸善にとって「フクロウ」はそれほど
歴史ある “ 大切な象徴 ” なのだということを
いまここに伝え残したい。

前述の彼の著作『犬物語』は、夏目漱石が
『吾輩は猫である』を発表する3年前
1902年(明治35年)の作品である。
そのインパクトの強い江戸っ子口調に
心をぐっと掴まれた。
「俺かい。俺は昔しお万の覆した油を
甞アめて了つた太郎どんの犬さ。
其の俺の身の上噺が聞きたいと。
四つ足の俺に咄して聞かせるやうな
履歴があるもんか」
( 内田魯庵著『犬物語』『社会百面相』(博文館刊行) より抜粋 )
舞台はお屋敷町・千代田区番町。
外国帰りの裕福なご令嬢に飼われている
まじりっけなしの日本犬である「俺」
飼い犬の視点から、次々と人間模様を描写する
この小説は、まさに『吾輩は猫である』の
先駆的作品ともいえる。
魯庵ならではの、鋭い風刺加減はもとより
この中に描かれている、プードルやマスティフ、
幅広い犬種には、目を見張るものがある。
この作品を発表した数年後に訪れる、
魯庵は、どう感じたのだろうか。

『 漱石全集 』第9巻 『門』 口絵より
明治 38年(1905年)
10月29日
卒業演奏会を聴きに、寺田寅彦と上野を訪れた
イルミネーションを見て、夜9時頃に
書斎の机には、1通の手紙。
差出人は「内田魯庵」
『吾輩は猫である』を賞賛する書面と
ともに同封されていたのは
27枚もの「猫の絵葉書」だった。

粋な計らいに漱石は感激したのだろう。
早速魯庵へ返事を書いた。
その追伸にこんな茶目っ気のある
一文があった。
猫儀只今睡眠中につき
小生より代わって御返事申上候
(『漱石全集』第27巻 『書簡集』より抜粋 (岩波書店刊行)

「百年の知己」と表現している。
その感覚の鋭さ、上品な知性を賞賛。
『猫』『坊ちやん』『草枕』『ロンドン塔』
そして『学鐙』に寄稿してもらった
「カーライル博物館」を挙げている。
また、漱石は気難しいところもあり、
何かと都合をつけ、来客を返してしまうことが
多かったというが、魯庵だけは、
突然訪ねて行っても、2〜3時間は話込んだという。
そんな嘘のつけない、正直な2人だからこそ、
お互い胸襟を開き、語り合うことが
できたのかもしれない。

▶︎ 旧幕府軍・土方歳三が11歳の時、奉公に来た歴史あるデパート
この街を舞台に『下谷広小路』を執筆していた
内田魯庵は脳溢血で倒れ、言葉を失う。
そして同年6月29日、61歳で旅立った。

巻頭の重役・部長ページより 丸囲みの人物・右上が「内田貢」
この社員写真帖が発行された5ヶ月後、魯庵は旅立った
“ 猫年か ”と思う位、数多くの「猫葉書」が
彼の元へ届いたという。
漱石が保管し続けたといわれる、数百枚にも及ぶ
「猫葉書」のうち、数枚が昨年公開された。
その中の1枚に、内田魯庵が送ったとされる
ニューイヤーカードが紹介されていた。

▶︎ 2016年5月4日付『朝日新聞』紙面 より
なんともかわいいらしい。
毒舌な魯庵が送ったカードとは
とても思えない。
「失敬極まる――
此奴め、ワンワンワンワン!」
( 内田魯庵『犬物語』より抜粋 )
魯庵からこんなお叱りを受けそうなので
そろそろこの辺で。
<参考文献>
『圕とわが人生』間宮不二雄著(丸善OB・日本図書館協会理事)
